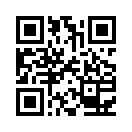2012年04月01日
秀月の雛人形 についての情報
場合によって、秀月の雛人形に関する見解は、それぞれ少しずつ違います。そんなことから、よく秀月の雛人形の比較がなされるのですが、さまざまな要因に注目して比較されることが多いようです。
もしかするとひな人形が売れなくて困ったお店が言いふらした迷信なのかも知れませんね。先ほどお姉様のことを歌っているのでそのお姉様の妹にあたる人物がひな人形を目の前にしてひな祭りの喜びを歌っている、と考えるのが妥当です。桃の節句の初節句には、お雛様を飾り、お祝いの膳を用意しましょう。女の子のいるご家庭ならほぼ確実にお祝いをするのがひな祭り。一口メモ・雛人形は少し離れてみる・・雛人形は全体の雰囲気を見ましょう、1〜2mは離れてみることをお奨めします、そうすれば全体のバランス、色などがよくわかります、あまりに近すぎるとアラばかりが気になり、セットとしての評価に迷いが生じます。開催中は町のあらゆるところに「ビッグ」なひな壇が出現し、ものすごい数のひな人形が飾られます。
古くから薬効があることで知られるヨモギは健康を守るために縁起が良い食材として重宝されています。言うまでもなく天皇家のお祝い事を変わり雛にしたものです。女の子の無事な成長を祝う大切な日本の伝統行事です。嫁入り道具に雛人形を持参するようになると、この流れはさらにヒートアップし、その家の見栄も手伝って豪勢な雛人形が作られるようになります。縁起の良い食材を使いたいときは、はまぐり(女の子の美徳と貞節を意味する)、よもぎ(薬用効果があり、菱餅の緑に使われています)、えび(えびの赤は生命を表します)、はす(見通しのいい人生)、豆 (健康でまめに働ける)などがあり、定番には「鯛」もあります。石段を使ったひな飾りと言えば「かつうらビッグひな祭り」というイベントも存在感があります。
子供と一緒に、ばら寿司や桜餅を作るのは楽しい思い出になるでしょうね。雛人形を飾ることは、生まれた子供が健康で優しい女性に無事に育つようにとの家族の願いがこめられています。過去にさかのぼると、変わり雛を見ているだけでその年の世相が何となく見えてきます。お盆になると京都の山に「大」の文字が光るイベントのことを全国的には「大文字焼き」と呼ぶのに対して京都では「五山の送り火」と呼ぶのに良く似ています。夫婦びな、三人官女、五人囃子、左大臣・右大臣、仕丁と橘と桜、お道具、乗り物と揃った7段飾りが立派ですが、各家庭の事情に合わせて、三段飾りや親王だけでも良く、ガラスセットも良いですね。道具も増え、容貌も写実的で、装束も複雑になりました。
ひな人形の飾り方について、これにはちゃんと理由があるのをご存知でしょうか。ひな祭りの食べ物と言えばどんなものを思いつくでしょうか。平安時代の貴族の子供たちが遊びの一環で「雛あそび」という名称の遊びをしていたことが記録に残っているそうです。せっかく良い物を持っているので、結婚して嫁いだ先で女の子が生まれた時に使いたいと願うのはごく自然のことですし、それは全く問題ないそうです。初節句は、赤ちゃんの健やかな成長と厄除けを願う行事です。江戸時代に入って、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けをするようになり、豪華な衣装の座り雛が登場してきます。