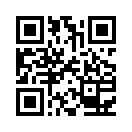2011年02月06日
秀月の雛人形 についての情報
皆さんは秀月の雛人形に関する情報に興味はありますか?
西日本のひな祭りはひな人形を川に流すという風習を残しているところが多数あります。ちらし寿司の中に果物を入れたものなど、デザート感覚で食べられるちらし寿司なんていうものもあります。このひいな祭りというのは、お察しの通りひな祭りのことです。いざ、購入する時でも、何軒かお店を見て廻りましよう。夫婦びな、三人官女、五人囃子、左大臣・右大臣、仕丁と橘と桜、お道具、乗り物と揃った7段飾りが立派ですが、各家庭の事情に合わせて、三段飾りや親王だけでも良く、ガラスセットも良いですね。桃花酒という名称がつけられたのは室町時代にまでさかのぼります。
雛人形を飾る場所をまず決めましょう。平安時代の上巳の節句に、草木や紙で作り、自分の厄を祓いとした流し雛が原型ですが、時代とともに発展し、七段飾り十五人揃えセットは雛飾りセットの定番です。ここではひな祭りの風習についてのお話をしたいと思います。この行事が、後に、自分の災厄を代わりに引き受けさせた紙人形を川に流す「流し雛」へと発展してゆきました。人形の産地ということはひな人形の生産も盛んです。鯛や、はまぐりのお吸い物とちらし寿司などのお祝いの膳を用意し、家族で健やかな成長を祝ってあげましょう。
いつしかこれが「ひいな遊び(おままごと遊び)」と合流して「ひな祭り」が生まれました。健やかに成長するように、家族で祝ってあげましょう。祝日というのは国家がお祝いをするために国民を休日にしようとするものです。実家からいくら援助していただけるかで、大体の予算が決まります。ひな祭りの起源はさかのぼること平安時代になると言われています。これの文化がひな人形にも表れ、現在では向かって左側に男雛が座っているのです。
ひな祭りにはひな人形、料理、お菓子、そしてなんと歌まであります。3つの色は、「一番上が紅色で“桃”、真ん中の白は“雪”、下の緑は“草”のことだよ」なんて話しながら作ったら、子供の中に季節感が育まれるかもしれません。言うまでもなく天皇家のお祝い事を変わり雛にしたものです。特にお雛さまは、赤ちゃんにとって災厄を代わりに引き受けると考えられている守り神のようなものですから、親としてお祝いしてあげて欲しいものです。この時代に桃花酒を3月3日に飲む風習があったので、たまたまそれがひな祭りと一緒になったのが始まりです。ということだそうです。