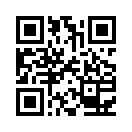2011年05月22日
秀月の雛人形 の紹介
秀月の雛人形 が、最近、なんだか妙に気になりませんか?。
女の子が産まれて初めて迎える桃の節句にお雛様を飾り、家族全員で赤ちゃんの健やかな成長と災厄よけを願ってお祝いするのが「初節句」です。古くから薬効があることで知られるヨモギは健康を守るために縁起が良い食材として重宝されています。その代表が流し雛で、人のけがれや災いなどを形代に移して川に流し不浄を祓う行事です。昔には五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)があり、貴族が季節の節目に身のけがれを祓う大切な行事でした。ひな祭りの食べ物と言えばどんなものを思いつくでしょうか。一口メモ・最近の平飾り台は、同じ材質と色の屏風とのセット販売が多く、台無しの要望は難しいものがあります、(茶色系の台、屏風にその傾向があります) 黒塗りのものは台無しで屏風のみの販売が可能です。
実家から贈ってもらった高価なひな人形だけに、子供に触らせるのは怖いと思うときは、子供が好きに遊んでいいように、ひな人形を一緒に手作りしてはどうでしょう?ペーパークラフトのお人形なら、破けてしまってもすぐに作り直せます。ひな人形は物によっては非常に高価なものもあります。平安時代の上巳の節句で、災厄を引き受けてくれた紙人形が原型で、室町時代になると、豪華なお雛様を飾って宮中で盛大にお祝いをするようになったのです。言うまでもなく天皇家のお祝い事を変わり雛にしたものです。単なるお祭りではなく、お七夜やお宮参りと同じく、女の赤ちゃんのすこやかな成長を願う行事で、お雛さまは、赤ちゃんに降りかかろうとする災厄を、代わりに引き受けてくれる災厄除けの守り神のようなものです。暦上では立春から2月中旬が飾り始める時期として良いとされています。
一口メモ・雛人形の大きさ・・小さい順に、柳、芥子、三五、十番、九番、八番、七番といいます。着物を着替えて今日は私も晴れ姿、というくだりがあるのですがこれはいったい誰なのかという話があります。人形の産地ということはひな人形の生産も盛んです。桃花酒という名称がつけられたのは室町時代にまでさかのぼります。つまり、子供の災いの身代わりになってくれるものなので、本来は次女、三女が生まれた場合、その子のためにまた新しく用意してあげるのが正しいしきたり。買い物に行く前に大体の置き場所、人形の種類、予算が決まったら、そのポイントに合った雛人形だけを見て回るようにしましょう。
2007年から1年前、2006年の変わり雛を見てみましょう。お店で見るときよりも実際に家で飾ってみるととても大きなものです。端午の節句は祝日なのにひな祭りは祝日ではないというのは女性差別だ、という指摘がなされたことがありました。もっとも最近では料理の幅が広がっているので、これらの伝統を踏まえつつより美味しい創作料理がたくさん生み出されています。しかも飾られるのは1ヶ所ではありません。現在のひな人形の主流につながる形式のものは古今雛といわれ、明和・安永年間(1764-1781)頃に江戸で流行したようです。