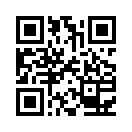2010年06月06日
秀月の雛人形 はこれ
秀月の雛人形 に関して、あなたが、初めて聞く新情報がみつかるといいですね。
子供と一緒に、ばら寿司や桜餅を作るのも楽しいですね。ひな人形は、愛娘を病気や怪我、災いから守ってくれる「お守り」の意味、つまり、災いの身代わりになってくれるものなので、本来は次女、三女が生まれた場合、その子のためにまた新しく用意してあげるのが正しいしきたりです。そんなタイトルの話はさて置き、この歌は4番まであります。菱餅というと何のことか分からない人も多いそうなので念のために説明しますと平行四辺形(?)に切られた板状のお餅を三色積み上げて飾るアレです。そして、ひな祭りといえば菱餅。これについえては具体的な言い分について割愛しますが、その言い分全てを読むと確かにごもっともだと納得させられてしまいました。
人形がやたら大きいとか、そういうわけではなく人形の数がびっくりなのです。縁起のいい食材とはどんなもので、どんな意味があるのでしょうか。最後の「母に感謝する」というのはまた別の話という気もしますが、そこには男の子という言葉は一切出てきません。群馬県渋川市に伊香保温泉があります。現在のひな人形の主流につながる形式のものは古今雛といわれ、明和・安永年間(1764-1781)頃に江戸で流行したようです。桃花酒という名称がつけられたのは室町時代にまでさかのぼります。
西日本のひな祭りはひな人形を川に流すという風習を残しているところが多数あります。おいしい手作り料理でお祝いしてあげたいものですね。これはなかなか世相をよく観察していて面白いなぁと思わされることが多いので、ここでは世相を反映した変わり雛についてお話しましょう。おうちにひな人形を飾って、素敵なパーティーを楽しんでくださいね。変わり雛というのはこのような意味があるのですが、ここでお話したいのはこの変わり雛ではありません。桃の節句の起原は、平安時代に遡ります。
菱餅の3つの色は、「一番上が紅色で“桃”、真ん中の白は“雪”、下の緑は“草”のことだよ」と説明も加えると、子供に季節感を植えつけられますね。つまり、男の子のお祭りは国家にとってお祝い事であって、女性のひな祭りはめでたくないのか、という理屈です。そもそもひな祭りという言葉は平安時代の貴族子女が遊んでいた「ひいな遊び」が起源になっていると言われており、そんな平安貴族が住んでいた京都はこの名称を使っているのです。一口メモ・雛人形の大きさ・・小さい順に、柳、芥子、三五、十番、九番、八番、七番といいます。親御さん方は可愛い孫のために大きな立派なものが好いというでしょうが、ご自分たちのライフスタイルなどを伝えて、あらかじめ予算を決めておくとよいでしょう。買い物に行く以前に大きさや種類、お値段のリサーチは十分にしておきましょう。