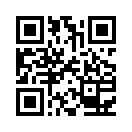2010年02月01日
秀月の雛人形 の真相
秀月の雛人形 と聞いて、まず思い浮かぶのは、皆さんなんですか?
お七夜・お宮参り・お食い初めのお祝いなど、赤ちゃんが産まれるとどこの家庭でも必ず行う行事です。女の子のいるご家庭ならほぼ確実にお祝いをするのがひな祭り。平安時代は、上巳の節句の日には野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。雛人形にも流行は1〜2年ではわかりませんが10年では随分と違ってきます、特に三人官女はご購入をおすすめします。時期的には昭和初期の頃から言われ始めたそうですが、そこには年長者からの戒めとして「片づけがキチンと出来ない娘はいい嫁さんにはなれない」という意味が込められています。平安時代に起原を持ち、高貴な生まれの女の子の厄除けと健康祈願のお祝いとしての「桃の節句」が、庶民の間にも定着して行ったお祝いです。
桃花酒という名称がつけられたのは室町時代にまでさかのぼります。江戸時代になると女の子の人形遊びと節句の儀式が結びつき、それが全国に広まりました。ここではひな祭りの風習についてのお話をしたいと思います。この行事が、後に、自分の災厄を代わりに引き受けさせた紙人形を川に流す「流し雛」へと発展してゆきました。平安時代は、野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。お菓子についても料理と同じように最近では色々とアレンジを利かせた面白いメニューがあります。
白酒もほしいです。ひな祭りはそれぞれの地方で独自の文化を伝えてきたイベントとして知られています。女の子のイベントということもあり、他にも赤系の食材が多く使われているのはこの海老のように縁起をかつぐ意味もあります。さて、ひな祭りの歌と言えば一番有名なのが「明かりを付けましょぼんぼりに…」という歌いだしのあの曲です。このイベントの主役はひな人形ではありません。京都に雛人形作りの名人が数家でたということです。
2007年から1年前、2006年の変わり雛を見てみましょう。他にも土着のイベントはありますが、ここまでしっかりと風習が残っているのはひな祭りを置いて他にはないとも言われていますから、ここではそんな全国各地にあるユニークなひな祭りを見てみることにしましょう。東日本のところでお話しましたように、ビッグひな祭りというイベントが千葉県の勝浦市と徳島県の勝浦町にあります。縁起のいい食材とはどんなもので、どんな意味があるのでしょうか。会場である鴻巣市役所に巨大なひな壇が設置され、そこにものすごい数のひな人形が飾られます。おうちにひな人形を飾って、素敵なパーティーを楽しんでくださいね。