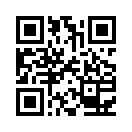2014年02月23日
大阪の雛人形 の検索情報
最近話題になりつつある大阪の雛人形ですが、一般的には、どのように認識されているのでしょうか。
姉妹や母子で共有すべきものではないのです。木目込み人形、親王飾り、三段飾り・人形は、二人、五人、十五人。ですが女の子が大きくなって自分のひな人形を嫁入りに持って行くと不幸になる、という言い伝えがあります。昔からある歌や童話は実は怖い、というどこかの本がありましたが、この「うれしいひなまつり」にもミステリアスな一面があるのかも知れませんね。これは非常に有名なものなのでお聞きになったことがある方も多いでしょう。飾る前日に桃酒やひし餅などの飾り物お供えします。
いつしかこれが「ひいな遊び(おままごと遊び)」と合流して「ひな祭り」が生まれました。その代表が流し雛で、人のけがれや災いなどを形代に移して川に流し不浄を祓う行事です。一口メモ・雛人形二人だけの飾り方を、通常『親王飾り』といいますね。次は西日本編です。天皇・皇后のうち身分の高いのは男性である天皇ということになりますから、男雛は向かって天皇から見た左側、つまり向かって右側に置かれることになります。桃花酒という名称がつけられたのは室町時代にまでさかのぼります。
さて、ひな祭りの歌と言えば一番有名なのが「明かりを付けましょぼんぼりに…」という歌いだしのあの曲です。その中の一つ「上巳(じょうし)の節句」が後に「桃の節句」となりました。さて、その指摘に対しての公式な回答というものがあるそうですので、それを見てみることにしましょう。あまりに有名なイベントなので、記念切手まで発行されています。このひな祭りは他の大掛かりなひな祭りイベントとはちょっと異なります。これの文化がひな人形にも表れ、現在では向かって左側に男雛が座っているのです。
先ほどお姉様のことを歌っているのでそのお姉様の妹にあたる人物がひな人形を目の前にしてひな祭りの喜びを歌っている、と考えるのが妥当です。嫁入り道具に雛人形を持参するようになると、この流れはさらにヒートアップし、その家の見栄も手伝って豪勢な雛人形が作られるようになります。これをお読みになって、よく見かけるひな人形の配列を思い浮かべてください。江戸時代に入って、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けをするようになり、豪華な衣装の座り雛が登場してきます。ひな祭りにはひな人形、料理、お菓子、そしてなんと歌まであります。ということは大変良い物であるということなので、大事に使えば末永く使うことが出来ます。