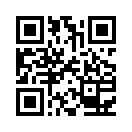2014年01月19日
大阪の雛人形 とは
皆さんは大阪の雛人形に関する情報に興味はありますか?
地域の活性化イベントとしては面白い企画だと思います。もしこどもの日がひな祭りの日だったとしたら、現在のようなゴールデンウィークは無かったわけですから、今さら変えると言われても困る人のほうが多いのではないでしょうか。厳密に言うと「桃の節句」というのは桃の花が咲く時期なのでまだ桃の実は手に入らないんですが、そんな細かいことは気にしなくても結構です。ひな祭りは子供が主役のイベントであることから、やはり子供が喜ぶような料理でありたいものです。これはなかなか世相をよく観察していて面白いなぁと思わされることが多いので、ここでは世相を反映した変わり雛についてお話しましょう。例えばこれを書いた2008年から見れば去年にあたる2007年の変わり雛はどんなものでしょうか。
こちら西日本の徳島ではそのイベントの徳島版が開催されています。このお姉様というのは「お嫁にいらした姉様」となっているので、この歌を歌っている本人には兄がいて、その兄のもとに嫁いで来た義理の姉が三人官女に似ているという説と、実の姉がどこかの家にお嫁に行ったということを歌っているという説。歌にも登場する五人囃子というのはお囃子を奏でて宮中を華やかに盛り上げるための楽団で、それぞれが太鼓・大皮・小太鼓・笛・謡の楽人です。女の子の無事な成長を祝う大切な日本の伝統行事です。たくさんありますので、東日本と西日本に分けてご紹介します。三人官女は宮中に仕える女官を示しており、随身の人形は右大臣と左大臣を示しています。
雛人形を飾る場所をまず決めましょう。時期的には昭和初期の頃から言われ始めたそうですが、そこには年長者からの戒めとして「片づけがキチンと出来ない娘はいい嫁さんにはなれない」という意味が込められています。片づけの出来ない娘はいいお嫁さんになれないよ・・という意味で、年長者からの惑めの気持ちがこめられています。鯛や、はまぐりのお吸い物とちらし寿司などのお祝いの膳を用意し、家族で健やかな成長を祝ってあげましょう。昔には五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)があり、貴族が季節の節目に身のけがれを祓う大切な行事でした。お餅はすぐに固くなってしまいますが、あられにすると長持ちします。
スポーツ界の話題をひな人形にした「ハンカチ王子雛」「イナバウアー雛」…もう2年前のことなんですね、早いものです。3つの色は、「一番上が紅色で“桃”、真ん中の白は“雪”、下の緑は“草”のことだよ」なんて話しながら作ったら、子供の中に季節感が育まれるかもしれません。この歌は古くからある歌にアレンジを加えて現在の童謡になったという経緯があります。子供と一緒に、ばら寿司や桜餅を作るのは楽しい思い出になるでしょうね。木目込人形セットは人形自体が小さく、全体をコンパクトに飾れ、品があります。この行事が、後に、自分の災厄を代わりに引き受けさせた紙人形を川に流す「流し雛」へと発展してゆきました。