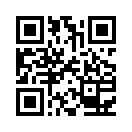2011年05月15日
大阪の雛人形 関連の情報
大阪の雛人形 については、はっきりしないところが、けっこうたくさんあるようです。
一口メモ・ケース入りの雛人形の利点と欠点・・ガラスケースの中に最初からある商品は便利ですし、ホコリをかぶらない、赤ちゃんにイタズラされない、などの利点があります。そして、ひな祭りといえば菱餅。おひな祭りの3月3日のことを「桃の節句」といいます。中には普通なら到底思いつかないようなものや、意外に簡単に出来るものなどがあり見ているだけでも結構面白いので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。先ほどお姉様のことを歌っているのでそのお姉様の妹にあたる人物がひな人形を目の前にしてひな祭りの喜びを歌っている、と考えるのが妥当です。それでは男の子のお祭りというと端午の節句です。
人形がやたら大きいとか、そういうわけではなく人形の数がびっくりなのです。この菱餅にはまたもや縁起を担ぐ意味が隠されています。こちら西日本の徳島ではそのイベントの徳島版が開催されています。桃の木には邪気を祓う力があるとされており、この時期に咲く花であることからひな祭りに飾られるようになりました。そもそもひな祭りという言葉は平安時代の貴族子女が遊んでいた「ひいな遊び」が起源になっていると言われており、そんな平安貴族が住んでいた京都はこの名称を使っているのです。というのも、人間がひな人形の衣装をまとってお雛様になるのです。
木目込人形セットは人形自体が小さく、全体をコンパクトに飾れ、品があります。たくさんありますので、東日本と西日本に分けてご紹介します。平安時代の上巳の節句に、草木や紙で作り、自分の厄を祓いとした流し雛が原型ですが、時代とともに発展し、七段飾り十五人揃えセットは雛飾りセットの定番です。もともとひな人形というのは子供達がおままごとをするためのもので、初期の頃は非常に簡素なものでした。厳密に言うと「桃の節句」というのは桃の花が咲く時期なのでまだ桃の実は手に入らないんですが、そんな細かいことは気にしなくても結構です。それでは、なぜ甘酒なんでしょうか。
平安時代は、野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。ところでひな祭りと言うと甘酒というイメージも付き物です。3つの色は、「一番上が紅色で“桃”、真ん中の白は“雪”、下の緑は“草”のことだよ」なんて話しながら作ったら、子供の中に季節感が育まれるかもしれません。その代表が流し雛で、人のけがれや災いなどを形代に移して川に流し不浄を祓う行事です。江戸時代はこのような工芸品の技術が飛躍的に向上した時代でもあるため、人形職人によって精巧な雛人形がたくさん作られ、それが競われるような時代になります。このお吸い物はほとんど確実にハマグリのお吸い物だと思います。