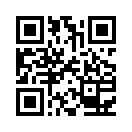2010年02月21日
大阪の雛人形 関連について
最近、大阪の雛人形の検討されてる方が多くなってきているようです。大阪の雛人形に関することが注目されてきているのでしょうか。
3番については右大臣の顔が赤いので、ひな祭りの定番である白酒を飲んだのかなという微笑ましい歌詞となっています。もちろん本物のひな人形を流していたら大変なことになりますので、折り紙で作った紙製のひな人形です。せっかく良い物を持っているので、結婚して嫁いだ先で女の子が生まれた時に使いたいと願うのはごく自然のことですし、それは全く問題ないそうです。平安時代は、野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。まずは東日本から。昔には五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)があり、貴族が季節の節目に身のけがれを祓う大切な行事でした。
ちらし寿司の中に果物を入れたものなど、デザート感覚で食べられるちらし寿司なんていうものもあります。奈良〜平安時代に日本の貴族階級に取り入れられたのが、日本での桃の節句のスタートといわれます。例えばパッチワークで作ったひな人形や、彫刻で作ったものなど、形にとらわれない独創的なひな人形がたくさんあります。ひな祭りの定番であるちらし寿司に使われている食材だけを見ても縁起のいいもののオンパレードです。雛人形をいつ頃購入するか?テレビCMはお正月明けによく見るけれど、11月あたりで早期販売などもありますね。大正天皇が即位儀式の際に西洋式に右側に立ったことにより、以後の天皇は右側に立つようになりました。
ひな祭りは日本の古い行事ですから、昔の人はお祝い事の席でその時の旬の食べ物を楽しんでいたのでしょう。これはなかなか意味深ですね。ひな人形は宮中の並び方をそのまま再現しているので、宮中の上位位置である左が最も身分の高い人が座ることになっています。雛あられは三色餅と同じように赤・緑・白の色がついていますので、三色餅と同じ毒や汚れを払う意味があるということです。普通は「お内裏様とおひな様 二人ならんですまし顔…」で始まる2番までしかないと思われています。雛人形は立春2月4日頃から2月中旬までに飾ります。
さてこのひいな祭り、名称はともかくとしてどんなお祭りなのでしょうか。その中の一つ「上巳(じょうし)の節句」が後に「桃の節句」となりました。着物を着替えて今日は私も晴れ姿、というくだりがあるのですがこれはいったい誰なのかという話があります。イチゴを使ったケーキやババロアなどは子供が喜ぶものばかりですし、「桃の節句」なのですから桃を使ったお菓子というのもよく活用されているようです。海老は赤色が生命を表しており健康や長生きを象徴しています。夫婦びな、三人官女、五人囃子、左大臣・右大臣、仕丁と橘と桜、お道具、乗り物と揃った7段飾りが立派ですが、各家庭の事情に合わせて、三段飾りや親王だけでも良く、ガラスセットも良いですね。