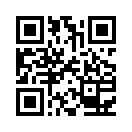2014年03月16日
陶器の雛人形 の検索情報
最近は、陶器の雛人形に新しい動きが出てきたようです。もともと、陶器の雛人形には、いろいろあるのですが、陶器の雛人形について検討をすると、やはり以下のようなことになるのでしょうか。
一番の理由はこれらの食べ物の旬がちょうどこの時期にあたるということが挙げられます。しかし江戸時代の町人は発想の転換がうまく、この規制を逆手に取って今度は小ささを競う雛人形が生み出されます。この時代に桃花酒を3月3日に飲む風習があったので、たまたまそれがひな祭りと一緒になったのが始まりです。平安時代は、上巳の節句の日には野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。特に大型のものは目立つため規制の対象となり、作られることはなくなりました。会場である鴻巣市役所に巨大なひな壇が設置され、そこにものすごい数のひな人形が飾られます。
筆者は大阪在住なので日常的に京都との関わりもあります。桃の節句の起原は、平安時代に遡ります。一口メモ・ケース入りの雛人形の利点と欠点・・ガラスケースの中に最初からある商品は便利ですし、ホコリをかぶらない、赤ちゃんにイタズラされない、などの利点があります。おいしい手作り料理でお祝いしてあげたいものですね。ひな祭りの定番であるちらし寿司に使われている食材だけを見ても縁起のいいもののオンパレードです。これの文化がひな人形にも表れ、現在では向かって左側に男雛が座っているのです。
一口メモ・雛人形の大きさ・・小さい順に、柳、芥子、三五、十番、九番、八番、七番といいます。また、子供が喜ぶ要素は味や食材だけではありません。雛人形を飾ることは、生まれた子供が健康で優しい女性に無事に育つようにとの家族の願いがこめられています。これだけ色々な文化が揃っているひな祭りというのは、いかに古くから人々に大切にされていたかが窺い知れます。この歌は古くからある歌にアレンジを加えて現在の童謡になったという経緯があります。これが時代とともに発展し、桃の節句として伝統行事になりました。
ちらし寿司、吸い物、菱餅、雛あられ…筆者が思いつくのはこんなところです。実際には3月中旬まで片づければ問題はないとされているのですが、なぜこのような言い伝えがあるのでしょうか。雛人形を大体決めましょう。桜の花のピンク色が女の子のイメージとぴったりなので、それを出された女の子本人が喜んでいたのが印象的でした。そんな理由なので、女の子のお祭りという意味合いとは特に関係はありません。女の子の無事な成長を祝う桃の節句のひな祭りは、大切な日本の伝統行事です。