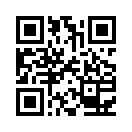2011年09月18日
陶器の雛人形 の関連情報
近頃、陶器の雛人形 について世間では色々な情報が交わされていますね。
こちら西日本の徳島ではそのイベントの徳島版が開催されています。もしかするとひな人形が売れなくて困ったお店が言いふらした迷信なのかも知れませんね。実のところ、筆者もこの文章を書くまで深く考えたことはありませんでした。平安時代の上巳の節句に、草木や紙で作り、自分の厄を祓いとした流し雛が原型ですが、時代とともに発展し、七段飾り十五人揃えセットは雛飾りセットの定番です。五つの節句があり、その中の一つ「上巳(じょうし)の節句」が後に「桃の節句」となりました。つまり、男の子のお祭りは国家にとってお祝い事であって、女性のひな祭りはめでたくないのか、という理屈です。
木目込み人形、親王飾り、三段飾り・人形は、二人、五人、十五人。桃の節句の起原は、平安時代に遡ります。特にこどもの日は子供のための祝日ですから、子供が色々な活動をするのに適している時期を選んだというのもあるのでしょう。桃の節句のひな祭り。西日本編の最後は、非常に有名なのが大分県日田市で開催される「天領日田おひなまつり」です。もともとひな人形というのは子供達がおままごとをするためのもので、初期の頃は非常に簡素なものでした。
言うまでもなく天皇家のお祝い事を変わり雛にしたものです。この法律は最近出来たような法律ではないので、先ほどのような指摘があったから男の子という文言を外したというわけではありません。 一口メモ・もし雛人形の顔にキズつけてしまったときはどうすればよいでしょうか?雛人形の顔部分を頭(かしら)といいます。さて、ひな祭りの歌と言えば一番有名なのが「明かりを付けましょぼんぼりに…」という歌いだしのあの曲です。もしこどもの日がひな祭りの日だったとしたら、現在のようなゴールデンウィークは無かったわけですから、今さら変えると言われても困る人のほうが多いのではないでしょうか。江戸時代に入って、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けをするようになり、豪華な衣装の座り雛が登場してきます。
ひな祭りは、高貴な生まれの女の子の厄除けと健康祈願のお祝いとしての「桃の節句」が、庶民の間にも定着して行ったお祝いです。つまり“リアルひな人形”です。おひな祭りの3月3日のことを「桃の節句」といいます。ですがこれはあくまでも西洋式だとして、伝統を重んじる京都では今でも向かって右に男雛を置く風習が残っています。それは、5月5日は祝日つまり休日であるのに対して3月3日は特に祝日というわけでもなく、普通の日だということです。もし迷ってしまったら、一番最初に気に入った雛人形にしましょう、二転三転する方もいらっしゃいますが結局最初のに落ち着く例が多いようです。