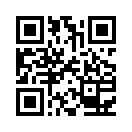2011年08月14日
陶器の雛人形 のニュース
陶器の雛人形 の情報をくわしく調査してみると、なかなか面白い事実に気がつきます。
子供たちはまだ体が小さいので、遠くから見ると本物のひな人形にも見えます。七段飾りは相当場所を取ります。江戸時代に入って、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けをするようになり、豪華な衣装の座り雛が登場してきます。筆者は大阪在住なので日常的に京都との関わりもあります。もちろん本物のひな人形を流していたら大変なことになりますので、折り紙で作った紙製のひな人形です。暦上では立春から2月中旬が飾り始める時期として良いとされています。
特にお雛さまは、赤ちゃんにとって災厄を代わりに引き受けると考えられている守り神のようなものですから、親としてお祝いしてあげて欲しいものです。もともとひな人形というのは子供達がおままごとをするためのもので、初期の頃は非常に簡素なものでした。五つの節句があり、その中の一つ「上巳(じょうし)の節句」が後に「桃の節句」となりました。また、子供が喜ぶ要素は味や食材だけではありません。西日本編の最後は、非常に有名なのが大分県日田市で開催される「天領日田おひなまつり」です。甘酒というのはその名の通り少ないながらもアルコールを含有している立派なお酒です。
お餅はすぐに固くなってしまいますが、あられにすると長持ちします。雛人形を購入するポイントについて考えてみましょう。さらに豪華なひな人形になると仕丁の人形もあります。京都に雛人形作りの名人が数家でたということです。ところでひな祭りと言うと甘酒というイメージも付き物です。ひな祭りの定番であるちらし寿司に使われている食材だけを見ても縁起のいいもののオンパレードです。
昔には五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)があり、貴族が季節の節目に身のけがれを祓う大切な行事でした。3番については右大臣の顔が赤いので、ひな祭りの定番である白酒を飲んだのかなという微笑ましい歌詞となっています。お殿様・お姫様と三人官女をセットしたのは、三段の雛飾りです。スポーツ界の話題をひな人形にした「ハンカチ王子雛」「イナバウアー雛」…もう2年前のことなんですね、早いものです。この歌は古くからある歌にアレンジを加えて現在の童謡になったという経緯があります。ひな祭りはそれぞれの地方で独自の文化を伝えてきたイベントとして知られています。