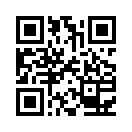2010年04月11日
陶器の雛人形 の口コミ
最近話題になりつつある陶器の雛人形ですが、一般的には、どのように認識されているのでしょうか。
いつしかこれが「ひいな遊び(おままごと遊び)」と合流して「ひな祭り」が生まれました。たくさんありますので、東日本と西日本に分けてご紹介します。立春というと2月4日ですから、ひな祭りからちょうど1ヶ月前からということになります。しかし江戸時代の町人は発想の転換がうまく、この規制を逆手に取って今度は小ささを競う雛人形が生み出されます。この行事が、後に、自分の災厄を代わりに引き受けさせた紙人形を川に流す「流し雛」へと発展してゆきました。この時代に桃花酒を3月3日に飲む風習があったので、たまたまそれがひな祭りと一緒になったのが始まりです。
雛人形を飾ることは、生まれた子供が健康で優しい女性に無事に育つようにとの家族の願いがこめられています。さて、ひな祭りの歌と言えば一番有名なのが「明かりを付けましょぼんぼりに…」という歌いだしのあの曲です。現在の雛人形はこれより少し大きいですが、当時のように1メートル以上もあるようなものはありませんね。姉妹や母子で共有すべきものではないのです。さて、その指摘に対しての公式な回答というものがあるそうですので、それを見てみることにしましょう。嫁入り道具に雛人形を持参するようになると、この流れはさらにヒートアップし、その家の見栄も手伝って豪勢な雛人形が作られるようになります。
過去にさかのぼると、変わり雛を見ているだけでその年の世相が何となく見えてきます。平安時代は、上巳の節句の日には野山に出て薬草を摘み、その薬草で体のけがれを祓って健康と厄除けを願いました。この歌にはあまり知られていない4番までがあると先ほど申し上げました。雛人形を飾って、友達を呼んでひな祭りパーティをして…どこにでもある光景ですね。それぞれのひな人形が何を示しているかはお分かりになりますよね。実のところ、筆者もこの文章を書くまで深く考えたことはありませんでした。
3つの色は、「一番上が紅色で“桃”、真ん中の白は“雪”、下の緑は“草”のことだよ」と話しすれば、子供に季節感が育まれますね。これを川に流すと一年間無病息災であるという言い伝えがあります。縁起の良い食材を使いたいときは、はまぐり(女の子の美徳と貞節を意味する)、よもぎ(薬用効果があり、菱餅の緑に使われています)、えび(えびの赤は生命を表します)、はす(見通しのいい人生)、豆 (健康でまめに働ける)などがあり、定番には「鯛」もあります。雛人形はいつ頃から購入するのがよいでしょうか?早期販売と銘打って、11月〜12月あたりから販売開始されるものは前の時期の在庫を吐いてしまって、今期の新製品を仕入れるという場合がありますので、お正月明けから2月中旬あたりでの購入がよいでしょう。この2番の歌詞にはちょっとした解釈論争があるのをご存知でしょうか。菱餅というと何のことか分からない人も多いそうなので念のために説明しますと平行四辺形(?)に切られた板状のお餅を三色積み上げて飾るアレです。